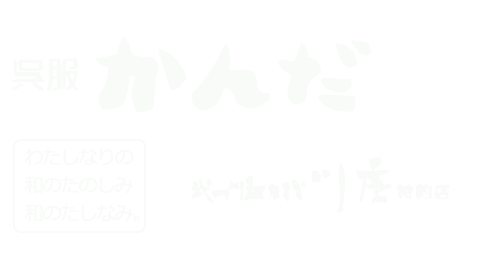1度は着てみたいと思っている着物
- でもどこに行けば買えるのか、着物に興味があるのにわからない。
- 誰に訪ねていいのかわからない。
- 着物を着始めたけど本当にこれでいいのか。
男性が着物を楽しむ上での様々な疑問を解消いたします。
テレビや映画で観た俳優への憧れや、ファッション好きが高じて着物に興味をもったりと、きっかけは様々。呉服かんだでは「着物を着たいんだけど・・」という方のお手伝いをさせていただきます。

1.着物を買う前に
● 着用目的を決めましょう。
着物も洋服と同じように、ある程度のTPOを考えて着用する必要があります。例えば、パーティーに出席するときに着るものと、近所を散歩する時に着るものは違います。
ただTPOというと、「なんだか難しそうだな」と思うかもしれません。ですから、1番最初に着物を着るときは、「いつ」「どこで」着たいのかを明確にすることをお勧めします。
具体的に着用目的がない場合でも、なんとなくでよいので、決めてください。
● 予算を決めましょう。

必要以上の出費を避けけるため、また不要な物を買わないためにも、予め予算は決めてください。特に初めて着物を買う場合、着物(長着)以外にも下着類や履物など以外に出費がかさみます。
また着物の場合、表示金額はお店によって「反物の価格」「お仕立て上がりの価格」など表示方法は様々です。
特にお支払いが可能な「最大限度額」は必須
● いろいろ見てみる。

初めて入った呉服屋さんでお買い物をされるのも「縁」ということで良いかとは思いますが、できればいろいろな呉服屋さんや売り場を見て回ることをお勧めします。
どういう種類の着物があるのか、着物以外の小物は充実しているか、値段は自分の予算に合うものが置いてあるかを実際に見てください。
実物で色や柄を確認し、反物・生地に触れてみましょう。
特に柄と素材はTPOを考える上でも重要で、何より着心地を左右します。
また店員さんの対応を見て信用できそうか、自分の話を聞いてくれるかも重要です。
そして何より、男物を置いてある呉服屋さんが少ないので、できればたくさん品物を置いてあるお店で選ばれるといいと思います。
● 店員さんに話を聞いてみる。
呉服屋さんに入ると「セールスされそう」「売りつけられそう」というイメージがある方も多いかもしれませんが、できれば最初は店員さんに話を聞いていろいろと教えてもらいましょう。
最初に「今日は買うつもりはない」「今日は下見に来た」とはっきり伝えれば無理なセールスをされることは少ないと思います。
同じ金額で同じ物を買うとしたら、できるだけ多くの情報を得られたほうがお得ですよね。
また、着る上で何が必要か、あったら便利な物など知らないことを知るチャンスです。
コーディネートや手入れのことなどは必ず聞いておきましょう。
その時の店員さんの対応で、このお店で買うかどうかを決めても良いでしょう。
2.着物を着るのに必要なもの
着用目的が決まり、予算を立て、気に入ったものが見つかったら早速着物を着たいですね!
では実際にお買い物に行く前に、着物を着るのには何が必要かを見てみましょう。
● 着物(長着)

一般的に着物というと長着を指すことが多いようです。
既製品や骨董市に出向いてアンティークを探すのも楽しみの一つですが、1番初めは自分に合ったサイズを知るためにも、反物を選び、自分サイズに誂ることをお勧めします。
着用目的や、着て行く場所によって選ぶ反物が変ってきます。
単衣(裏地なし)・袷(裏地を付ける)で迷ったら、特別に着用日が決まっていない場合、袷で仕立てると1年を通して着用期間が長くなるので袷が良いでしょう。
ただ、木綿やウールなどのふだん着はその限りではありませんので、店員さんと相談してください。
種類をある程度絞ってから、後は自分の好きな色・柄を選んでください。
反物を選ぶ際は必ず鏡の前で体に合わせてみましょう。
最初はどのような物が自分に合うのか分からないことが多いので、洋服の色の好みと同じようなものを選ぶと間違いが少ないようです。
● 帯

男性用の帯は一般的に「角帯」と「兵児帯」がありますが、まず最初に買うには角帯がよいでしょう。
素材は化繊や木綿、交織りから正絹(ショウケン:絹100%のこと)まで様々です。
締めやすいのは正絹で金額もそこそこしますが、1度良い物を知るためにも正絹の帯をお勧めします。
洋服のネクタイに近い感覚で、着物とのコーディネートを考えながら気に入った色柄を選んでください。
● 長襦袢

長着の下に着るものです。
衿の部分に別布で半衿を付けて着用します。
素材は正絹、メリンス、化繊がほとんどで、夏用として絽や麻などがあります。
そもそも男の着物は無地で地味な色目の物が多いので、着物姿にこだわるとしたら履物と羽織の裏地、長襦袢になりますが、見えるのは衿の部分と袖口だけなので、最初のうちは袖口の色と着物が合うかを気にするだけでよいでしょう。
ただし、着物と一緒に作らないときや、既製品・アンティークを買うときは裄(背縫いから手首まで)の長さと着丈に気を付けてください。
長襦袢の裄の長さは着物から5mm~1cm程短くするのが標準的です。
また着丈は着物よりも数センチ短ければ問題はないですが、10cm以上短いと裾さばきが悪くなり、また、着物の裾が翻ったときに少しみっともないように思います。
● 肌襦袢

肌襦袢とは洋服で言うと肌着・アンダーシャツにあたります。
UネックやVネックのシャツでも代用はできますが、着物を着たときの心地よさを生かすためには、肌に密着しない肌襦袢の着用がお勧めです。
素肌の上に直接着るものなので、素材は着ていて気持のよいものがいいでしょう。一般的なのは汗も吸い取ってくれる晒の物です。
人は暑くても寒くても汗をかくので、汗で着物や襦袢を傷めないためにも必ず着用してください。
男物の着物を売っているお店で販売していますが、素材によって金額は様々です。
最初の1枚は1,000円~2,500円程度の既製品を買っておけば十分でしょう。
また当店ではサイズにこだわる方に、オーダーも承っています。
● ステテコ

半襦袢と合わせて長襦袢の代わりに着用するのが一般的ですが、長襦袢を着る際にも、長襦袢の生地を傷めないため、また、裾さばきを良くするためにも着用するとよいでしょう。
素材はキュプラが滑りが良いので着やすく、色は紺・グレー・水色・白が一般的です。
ステテコの代わりに裾除け(腰巻)を着用するのもお勧めです。
形は女性物と同じで、サイズが異なります。
● 履物

「おしゃれは足元から」とはよく言いますが、せっかく素敵な着物を着ていても履物が合わないと、全体のコーディネートも台無しです。
男性用の履物は基本的に「草履」「雪駄」「下駄」の3種類です。
白い鼻緒に畳表の雪駄はフォーマル用として使用します。
紬やお召などの正絹のカジュアルな着物には竹皮や籐表の台の雪駄がお勧め。また皮革やエナメル、ホースヘアーなど、お洒落用として使える雪駄は素材も様々です。
下駄は木綿やウールや浴衣など普段着物向きです。改まった場所に着て行かないのであれば紬にも合わることもでます。
草履は少し改まった席に出る時などに合わせると、コーディネートが上品にまとまります。
鼻緒は細めの物が足元がすっきりとしていいのですが、慣れないうちは太めの鼻緒の物を選んだほうが良いでしょう。
鼻緒の裏地に本天という柔らかい素材の物を使っている鼻緒は足当りもやさしく、履いていて疲れません。
履物に関しては書き始めると長くなるので、また改めて別頁で書かせていただきます。
● 足袋

着物を着るときに一番最初に身に着けるものが足袋であることが多いかと思いますが、足袋は決して靴下の代わりではなく、全体のコーディネートを引き締める重要な役目を担っています。
男物の足袋は礼装用は白足袋を使用しますが、それ以外は紺足袋や黒足袋が一般的です。
最近では黒や紺以外の色足袋や柄物の足袋を履いている方も多く、足元のお洒落に気を使うのは素敵なことだと思います。
もちろん男性でも足袋は白足袋しか履かないという方も。
礼装以外でしたら、着物とのバランスを考えて自由にコーディネートされるとよいでしょう。
どれにするか迷ったら、紺足袋がオールマイティに使えます。
● 腰紐

長襦袢(または半襦袢)と着物(長着)を着るときに腰で締める紐として2本必要です。
素材はモスリン(ウール100%)で白無地の物がお値段も安く最初に揃えるのによいでしょう。
柄物や色物を使用し見えないところにもこだわると着物を着るのがいっそう楽しくなるかもしれません。
しかし、着物や襦袢との摩擦で色落ちしないかを必ず確認してください。
素材はモスリンの他に正絹や化繊の物があります。
また着物用の腰紐の代わりとして博多織で広幅の「男締」や「きものベルト」
など便利な着付け道具が販売されていますので、着付けに不安がある方は色々試してみるのも1つの方法です。上記の物を揃えると着流しスタイルの完成です!!少しよそ行きの服装にするためには、羽織が必要。
● 羽織
お待ちください
● 羽織紐

3.「初めての着物」にお勧め
お待ちください